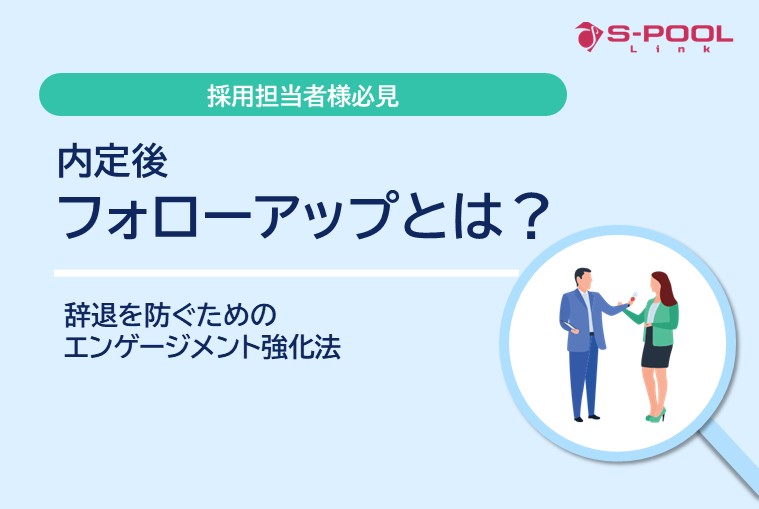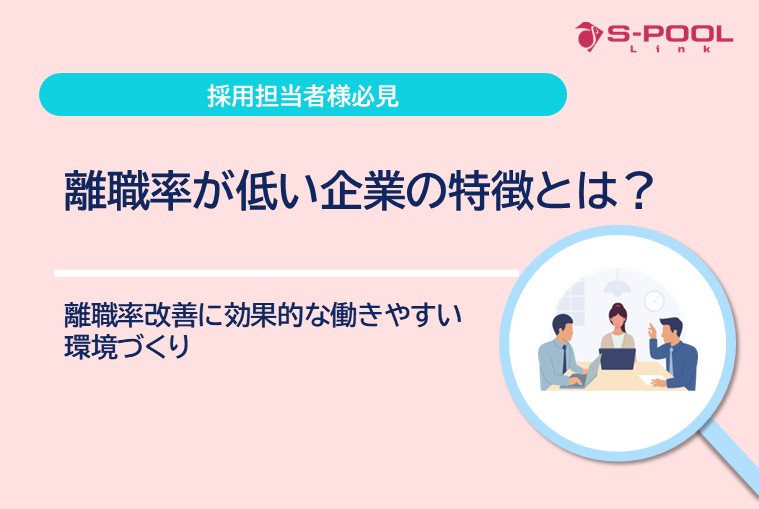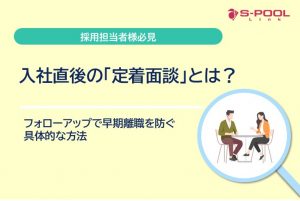
近年、新入社員の早期離職は多くの企業が直面する課題となっています。
厚生労働省の調査によると、新卒社員の約30%が3年以内に離職しており、その多くは入社直後の数ヶ月間に集中しています。
このような早期離職を防ぐために効果的なアプローチが、「定着面談」です。
定着面談は新入社員の声を早期に拾い上げ、必要なサポートを提供することで、ミスマッチや不安の放置による離職を防ぎます。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」
本記事では、定着面談の目的や実施方法、具体的な効果、さらに成功事例まで詳しく解説します。
自社の定着率向上や早期離職防止の施策を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1.「定着面談」とは?その目的と重要性
「定着面談」とは、新入社員と上司・人事担当者が行うフォローアップ面談のことです。
入社1ヶ月後・3ヶ月後・6ヶ月後といった節目で実施され、新入社員の不安や疑問を解消し、職場への適応を支援する場となります。
主な目的
1.1. 早期離職リスクの軽減
不安や不満を早期に発見し、解決に向けた具体策を提示。
1.2. 心理的不安の解消
面談を通じて得たフィードバックを制度・職場づくりに反映。
1.3. 信頼関係の構築
上司や人事が関心を持って耳を傾けることで、社員が安心して働ける環境を醸成。
2.なぜ「定着面談」が早期離職防止に効果的なのか
定着面談は単なる雑談ではなく、「離職の予兆を早期に発見し、改善へつなげる仕組み」です。
2.1. 不安の軽減
業務や人間関係に対する不安を解消することで、早期離職の引き金を防ぎます。
2.2. 離職の兆候を早期発見
「意欲の低下」「孤立」といった兆候を見逃さず、早めに手を打つことができます。
2.3. 職場改善につなげる
個々の声を集めることで、研修制度や配属体制の見直しなど組織全体の改善にも役立ちます。
3. 定着面談を効果的に活用する具体的方法
3.1. 面談前の準備
・情報収集:履歴書や入社面接時の目標を再確認。
・ゴールを設定:適応状況の把握やキャリア希望の確認を明確化。
3.2. 面談時のポイント
・心理的安全性を確保:リラックスした雰囲気づくり。
・具体的な質問:「どの業務が難しいか」「職場で困っていることはあるか」など具体的な質問で相手の状況を把握する。
・課題の共有と解決策提示:小さな不安も放置せず、即時に取り組む姿勢を示す。
3.3. 面談後のアクション
・進捗確認:改善状況を定期チェック。
・情報共有:関係者に必要な範囲で共有し、チーム全体でフォロー。
4.定着面談の実施で得られる3つのメリット
4.1. 早期離職の抑制
問題を放置せず対応することで離職を防止。
4.2. モチベーション向上
「自分の意見が尊重されている」という実感がモチベーションにつながる。
4.3. 職場改善
面談で得た情報をもとに研修や制度を改善し、組織全体の生産性を高める。
5.成功事例:定着面談で離職率を改善した企業
成功事例
事例1:サービス業A社
・施策:入社1ヶ月後と3ヶ月後に定着面談を導入。結果をもとに追加研修を実施。
・成果:3ヶ月以内の離職率が 30% → 15%に改善。
事例2:製造業B社
・施策:面談を通じて「職場のコミュニケーション不足」を課題として特定。社員交流イベントを企画。
・結果:1年後の離職率が 20%改善。
6.まとめ
「定着面談」は、新入社員の不安解消・職場適応支援・信頼関係構築に効果的な施策です。
形式的な面談ではなく、課題を発見し改善へつなげる仕組みとして継続的に運用することで、早期離職を大幅に防ぐことができます。
エスプールリンクでは、採用活動とフォローアップ施策をトータルでサポートしています。
・採用戦略設計:企業ニーズに合わせた採用計画を策定
・フォローアップ支援:定着面談やオンボーディング体制の設計をサポート
詳細資料のご請求や個別相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-
2025年02月27日
-
イベント
-
セミナー
-
レポート
-
お役立ち情報
エスプールリンクについて エスプールリンクは応募受付代行サービス『OMUSUBI』、WEB面接代行サービス『Faceview』を主軸に、企業様の採用支援を行っている企業です。飲食 …
-
-
2025年10月22日
-
お役立ち情報
採用活動を成功させる上で、内定辞退を防ぐことは重要な課題の一つです。近年、複数の内定を獲得する求職者が増える一方で、内定辞退率が上昇傾向にあり、企業は採用活動にかけたコストや時間を無駄にしないための対 …
-
-
離職率が低い企業の特徴とは?離職率が低い企業の3つの特徴とは?離職率改善に効果的な環境づくり
2025年10月08日
-
お役立ち情報
「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう…」「人材が定着せず、採用コストばかり増えている…」こんなお悩みを抱えている経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。離職率が高いと、採用コストや教育コストが増 …
-